娘が家に帰ってきてから、3日が過ぎました。
あの重苦しい再会の日から、私たちの家は、時間が止まったかのようでした。
私は、前の記事で決めた通り、娘を質問攻めにすることをぐっとこらえ、ただ「おはよう」「ご飯できたよ」「おやすみ」と、最低限の言葉だけをかけるように努めました。
娘も、ほとんどの時間を自分の部屋で過ごし、食事の時だけ、リビングに姿を見せる。
夫も私も、何から話していいか分からず、食器の音だけが気まずく響く。そんな、薄い氷の上を歩くような、ピリピリとした数日間でした。
「あの子は、このまま、心を閉ざしてしまうんだろうか…」
そんな不安が、日に日に大きくなっていた、ある日の夜のことです。
沈黙を破った、娘の小さな声
夫が残業で遅くなり、私が一人でリビングのソファに座って、ぼんやりとニュースを眺めていた時でした。
お風呂から上がった娘が、私の隣を通り過ぎ、冷蔵庫に向かう。そして、コップに水を注いだ後、部屋に戻ろうとして…ふと、足を止めました。
「……あのさ」
娘から話しかけられるなんて、思ってもみませんでした。
驚いて顔を上げると、娘は、私と目を合わせないまま、小さな声で続けました。
「……別に、お母さんとか、お父さんのことが、嫌いになったとか、そういうんじゃないから…」
心臓が、ドクンと大きく鳴りました。
娘が、やっと、自分の言葉で話し始めた。
私は、テレビを消し、娘に向き直りました。「うん」と、ただ相槌を打つことしかできませんでした。
「疲れた」…娘が絞り出した、本当の理由
娘は、リビングのテーブルの椅子に、ぽつんと座りました。
そして、コップを握りしめたまま、うつむき加減で、ゆっくりと、途切れ途切れに話し始めました。
「学校…なんか、もう、疲れた」
「…いつも一緒にいたグループの子たち、いるんだけど…。最近、なんか、私だけ、誘われないっていうか…。LINEのグループ、別にあるみたいで…」
娘は、地域の進学校に通っていました。
私は、勉強も大変だろうけど、友達にも恵まれて、そつなくやっていると、勝手に思い込んでいたのです。
「この間、インスタ見たら、私以外のみんなで遊んでる写真が上がってて…。あ、私、もう、いらないんだなって…」
「『さとみちゃんは、頭いいからいいよね』って、みんな言うけど、そんなことなくて。本当は、授業についていくの、すごい必死で…。でも、そんなこと、誰にも言えないし…」
娘の目から、こらえていた涙が、ぽた、ぽたとテーブルに落ちました。
「家に帰っても、お母さん、『学校楽しい?』って、聞くじゃん…」
「…『楽しくない』なんて、言えるわけ、ないじゃん…」
「もう、なんか、全部が嫌になったの。勉強も、友達も、期待されてる自分も。全部リセットしたかった。誰も私のこと知らないところに行って、ただ、ボーッとしたかった…」
雷に打たれたような、衝撃
娘の告白を聞きながら、私は、言葉を失っていました。
怒り? 悲しみ?
そんなものじゃありませんでした。
ただ、雷に打たれたような、強い衝撃と、深い、深い後悔でした。
私は、娘のことを、何も分かっていなかった。
娘が、進学校で必死にもがいていたこと。
スクールカーストの中で、SNSで、たった一人で傷ついていたこと。
私が「良かれ」と思ってかけていた、「学校楽しい?」という何気ない一言が、娘をどれだけ追い詰める、呪いの言葉になっていたか。
娘が時折見せていた、口数の減少や、部屋にこもりがちな態度。
私はそれを、「思春期だから、そんなものよね」と、どれだけ都合よく解釈し、見過ごしてきたことか。
娘は、ずっと、SOSを出していた。
この家の中で、たった一人で苦しんでいた。
それに気づかず、「普通」の日常を押し付けていたのは、他の誰でもない、母親である、私だったのです。
「ごめんね」…やっと言えた、たった一言
「…そうだったんだね」
やっと絞り出した私の声は、ひどく震えていました。
「気づいてあげられなくて、ごめんね」
「そんなに、つらかったんだね…。ごめんね…」
私は、娘の前に崩れるように座り込み、娘の手を握っていました。
娘は、何も言わず、ただ、声を殺して泣き続けていました。
あの冷たい再会の日とは違う、温かい涙。
1ヶ月ぶりに、私たちの間に、止まっていた何かが、ゆっくりと流れ出したような気がしました。
娘の家出の理由は、家庭への反抗などではなく、真面目で、優しすぎた娘が、一人で抱えきれなくなった「生きづらさ」そのものでした。
私は、この日、改めて決意しました。
この子の苦しみを、今度こそ、絶対に一人で抱えさせない。
この家を、本当の意味で「安全な場所」にしなくてはならない。
長い、長い夜は、まだ明けたばかりでした。
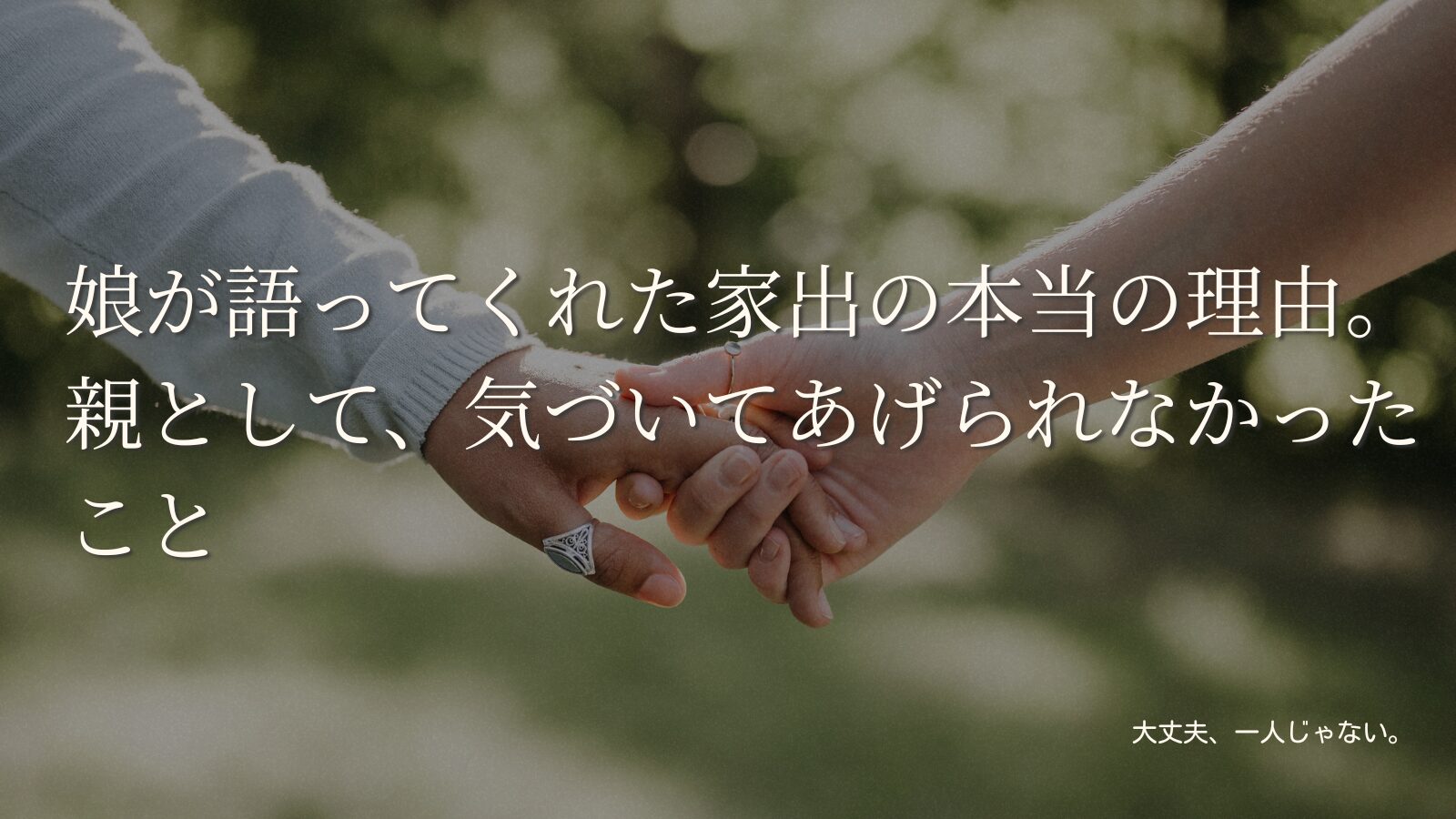

コメント